2024年7月13日(土)第9回東京文芸部「書く会」を神保町(水道橋)のレンタルスペースで開催しました。
今回は13名(私:1人・男性:5人・女性:7人)の参加でした。
今回は小説を書いた方が9名、エッセーを書いた方が3名、脚本を書いた方が1名でした。
皆様、ご参加ありがとうございました。
また、ご事情があって来れなくなってしましまった皆様もぜひ次回お越しくださいね。ご参加お待ちしております。
ご興味が湧いた方はぜひお越しください。
本日のワークショップ
本日も創作体験ワークショップをやりました。※東京文芸部では、せっかく集まっているので一人ではできない体験をしようというのをコンセプトにしたワークショップを時間があればやります。
今回は他己紹介を皆さんにやってもらったのですが、人数が増えて思っていたよりカオスになりややスベりしたような気がします笑
が、その後なんだかんだ盛り上がりました~!(たぶん)
本日の創作物
今回の作品はお題として私がお出しした「雨」「遊園地」で書いた方もいれば、もともと持っていたアイディアで作品を書いた人もいました。
皆さんが創作していただいた中から、掲載許可をいただいた作品を掲載します。今回は秘密派の方が多いですが、参加者13名、皆さん書いております笑 いつも掲載許可してくださっている皆様ありがとうございます。
「男の子」
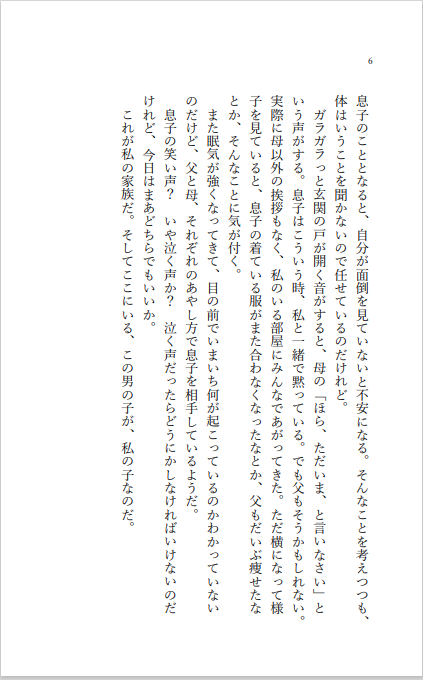
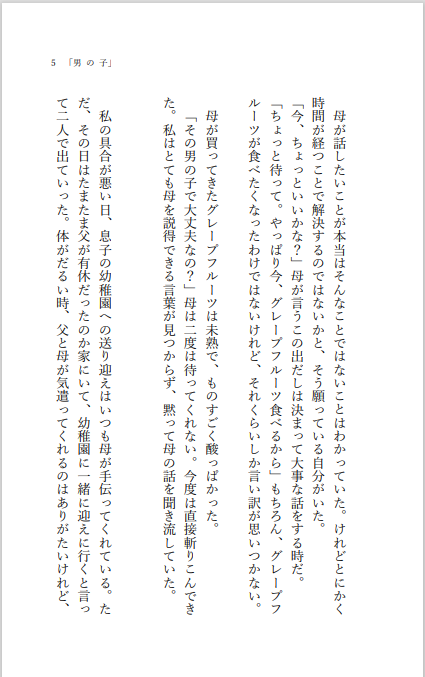
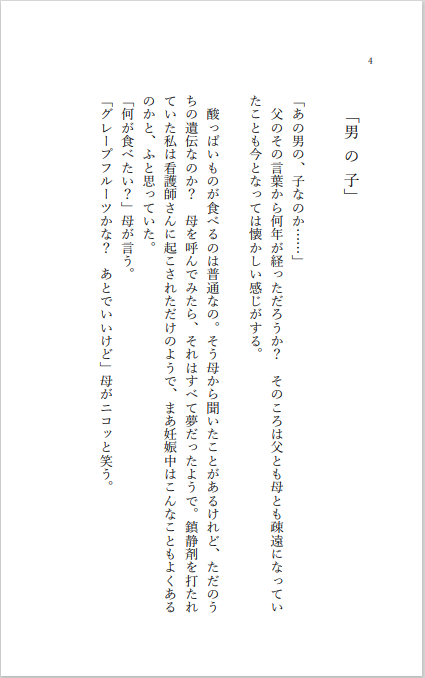
「乗り越える」
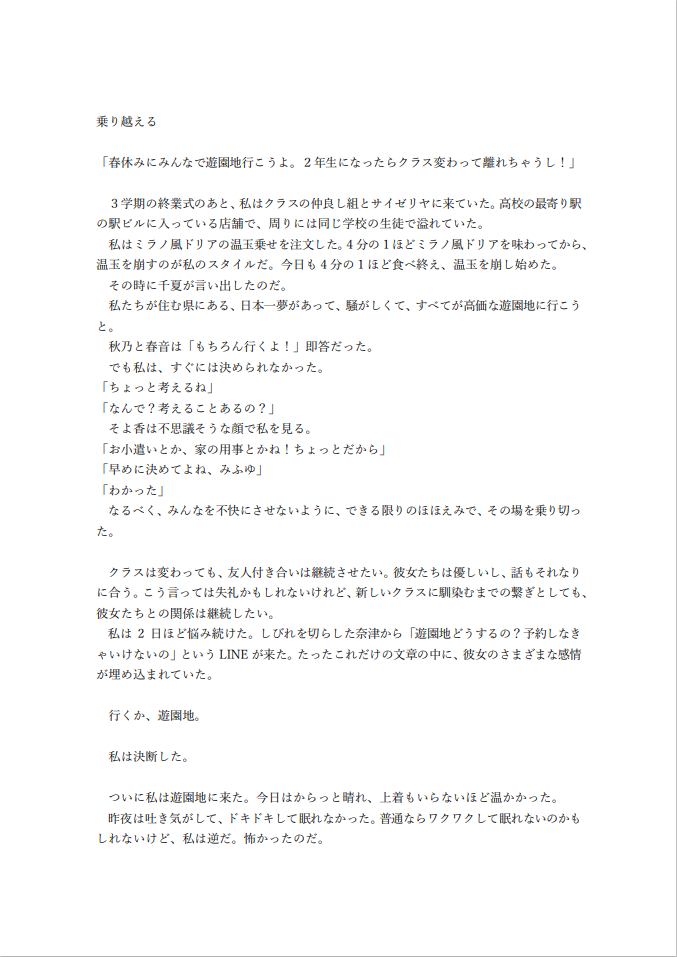
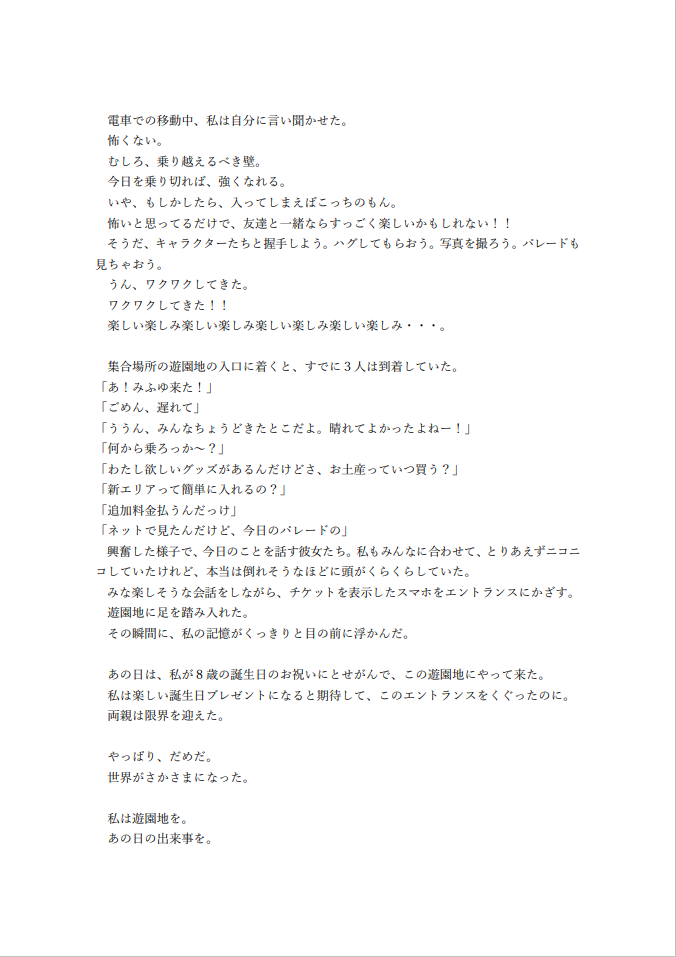

「欲しいもの、行きたいところ」
「遊園地に行きたい」と言ったら、真山町公園に連れて行かれた。滑り台が窮屈でスリルのない腑抜けになっても、私の遊園地は真山町公園だった。 でも遊園地は嫌いではなかった。
ブランコを漕いで、視界が空になった時、小さな死神が耳元で息を吐く。 鎖を握る手が白くなるほど、小さな長方形に乗せた足のひらの感覚が鋭敏になるほど、私の心は叫び、跳ねた。
「水族館に行きたい」と言ったら、真山町公園の池に連れて行かれた。鯉の餌は家のあちこちに落ちている小銭を使って買った。父は、当然のように代金入れにお金を入れなかった。鯉が馬鹿みたいに大口を開けて空気を食むのを、父はポケットに手を入れて見ていた。
私は、餌袋をひっくり返してしまいたい気持ちを、餌と一緒に丁寧に池に投げ入れた。投げ入れ続けた。ベニヤ板で出来た手作りの代金入れは、いつも空っぽな気がした。代金箱の正面にはラミネートされた紙が画鋲で貼り付けられていて、「無賃は盗人! 犯罪です!」と消えかけの赤で訴えている。私は父が犯罪を犯さないように、毎回百円をこっそり入れていた。
そうして、私の機械的な餌やりが終了すると、父はポケットに手を入れたまま家の方向へ回れ右をして歩き始めるのだった。
父と私の後ろで、鯉はまだくちょくちょぐちょぐちょと唇を鳴らしているのが大嫌いだった。大嫌いだった。今だって、大嫌い。
「動物園に行きたい」と言ったら、二人でバスに乗る。
真山町公園を過ぎ去っていく時、案外小さいことに少しだけ驚いた。動物園は真山町公園より広くて、人が多くて、うるさかった。父は走る馬を応援する時にだけ叫び、跳ねた。それがその時飼っていた鶏にそっくりだと思った。動物園は賭けである。負ければ、父の体の輪郭に沿って発せられる電流のような不機嫌を浴びながら、ささやかに笑う。私はその時、最も子供だった。
しかし勝てば、ファミレスのメニュー選び放題が与えられる。私はそこでバニラのソフトクリームを一つだけ頼んだ。私がパフェのページを見ている時は、なんとなし父の目が怖かった。
「春ちゃん、かわいい」
男はキリンのぬいぐるみを持った私にそう言った。帰りのバスはそれなりに混んでいて、汗臭い人間の匂いがした。
「ありがとう」
私はささやかに笑う。男はもう一度、かわいいと繰り返した。動物園のお土産コーナーは百円ショップでも買えそうな雑貨が並んでいて、「当園オリジナル!」の札のついたマグネットは赤い創英角ポップ体で動物園の名前が載っていた。しかし私は、キリンのぬいぐるみを買った。そのお土産コーナーで一番高い売り物だった。
「春ちゃん、それ、すっごい……いい……」
男は暖色光だけを支えにした暗がりの空間で、馬鹿みたいに力の抜けた声を出しながら、私の頭を撫でた。
「上手、上手」
私は目の奥で空虚を捉えながら、目の前の餌をしゃぶった。
鯉は大嫌いだった。
しかし、それで良いのだ。
父はどうして私を外に連れ出したのか、私に鯉の餌やりをやらせたのか、私のことを本当は、もしかしたら、というのは、考える必要のないことだったと分かっている。
父は鯉のような女とどこかに行ってしまった。
「遊園地に行きたい」
と私が言ったので、男はそれを叶えた。
お姫様が住むお城も、動物が抱擁してくれる家も、キャーキャー叫ぶためのアトラクションも全てを回って、足が痛くなるまで遊んだ。
「春ちゃん、すっごく楽しんでたね」
私は、肯定とも否定とも取れるような頷きを返す。男がそれを肯定と受け取ることは知っていた。
「ねぇだからさ、今度こそさ、愛し合おうよ」
「ねっ」
私は空を見上げた。閉園の音楽が背中を押している。
曇天、雨が降るのだろか。暗い空は厚い雲でさらに暗さを増していた。
「私ねぇ、遊園地に行きたいの」
男は、行ったじゃないと言う。
私は首を振った。
「遊園地に、行きたいのよ」
ゲートを通る私たちを、最後までスタッフが手を振った。
「雨の日の遊園地」
日が落ちて閉園のアナウンス鳴ってからしばらくが経過すると、遊園地の敷地内は照明以外が暗闇だった。昼間は豊かだった彩色は、全ての表現力を失い単色となっている。照明の白色光が照らすわずかな箇所だけがほんの少しの色を持っていたが、その失われかけた色素を識別する余裕はない。
秋の寒い日で、ひどい雨が降っていた。ぽつぽつと鉄骨に落ちる雨の一粒一粒は、またたくまにざぁざぁととめどなく鉄骨に降り注ぐようになり、巨粒となって鉄骨を殴るようになり、その体積で空間の大部分を占めるようになった。
その頃に、園の端を目指して移動を始めた。時間もなかったので雨具もなく、動いた。髪も衣服もひどく濡れており、身体の熱は徐々に奪われていく。横殴りの激しい雨が目玉に直接ぶつかり、半自動的に瞼が閉じる。しかし私は前を見なければならないので、意思を持って顔を上げて前を見ようとする。髪や顔から垂れてきた大粒の水が目玉と瞼の中に入り込み、視界がぼやけてくる。そしてその隙間に入り込んだ雨水を排出するために大きく瞬きをせざるをえなくなる。そのような水滴まみれの顔を腕で拭う。
「やらない理由、やる理由」
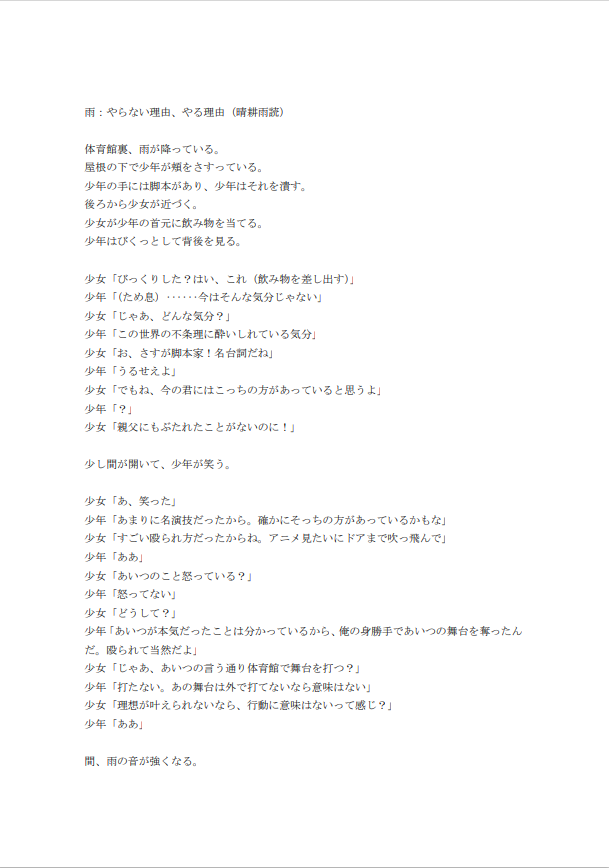
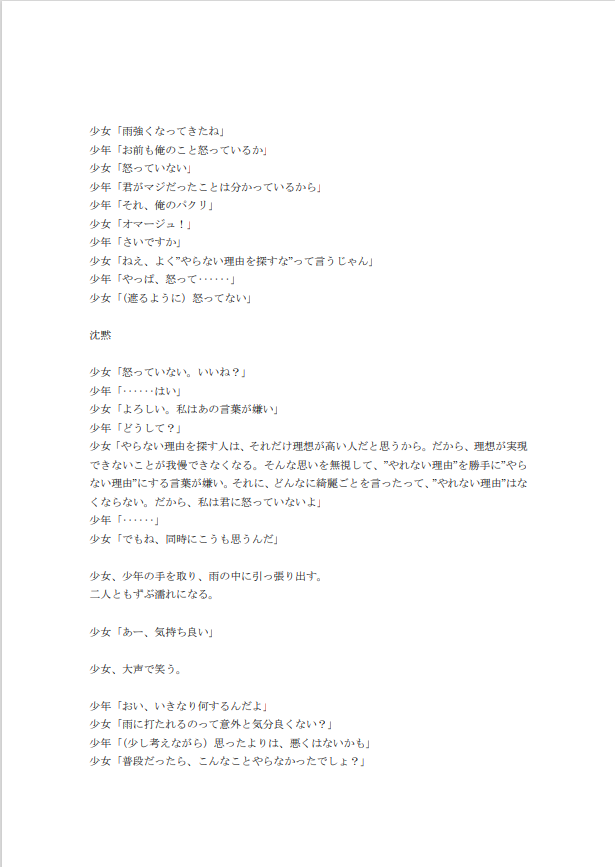
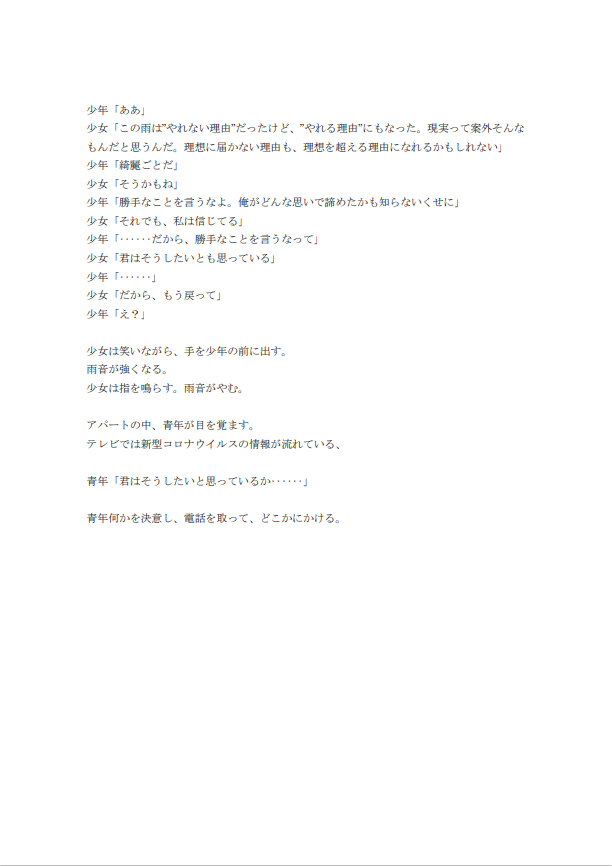
終わりに
終わったあとは、予定が空いていた8人と、ちょうど近くで飲んでいた前回参加者の計9名で飲み会にいきました。
文芸部っぽいというか、よく考えると心配な話題を爆笑しながら語りあっている皆様などもいて、とても楽しかったです。
ご興味が湧いた方はぜひお越しください。



